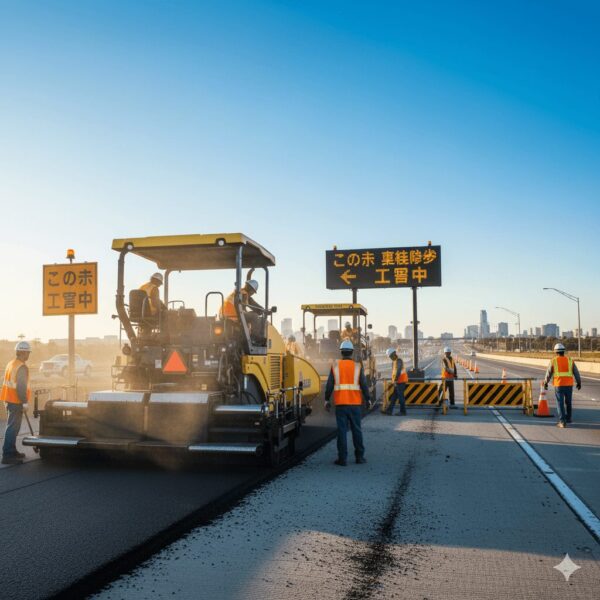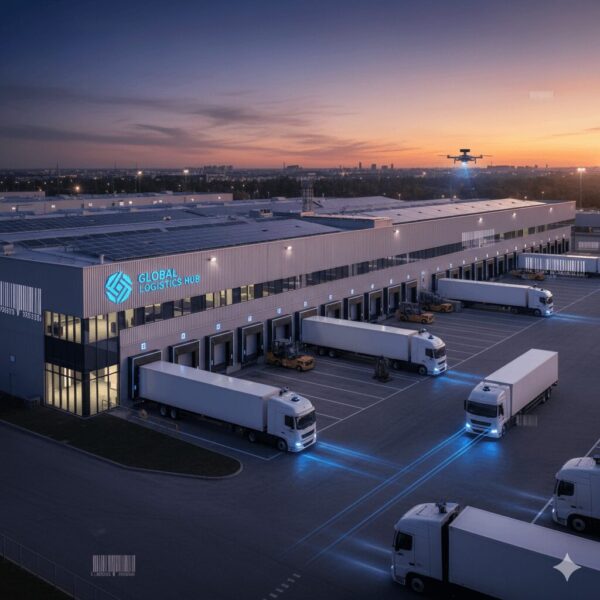公開日:
常磐道に新設IC、「つくばみらいスマートIC」が正式名称に決定!
- 道路
- 業界ニュース

2025年2月27日、茨城県つくばみらい市とNEXCO東日本関東支社は、常磐自動車道に新設されるスマートインターチェンジの名称を「つくばみらいスマートインターチェンジ」と正式に決定しました。これにより、地域の交通利便性向上や産業活性化が期待されるほか、高速道路の利用促進にも寄与する施策となります。
地域の発展を加速!つくばみらいスマートIC導入の背景とは?
つくばみらい市は、東京都心から約40km圏内に位置し、首都圏とのアクセスが良好なエリアです。近年、つくばエクスプレス(TX)沿線の都市開発が進み、特にみらい平地区では住宅地の拡大とともに、人口増加が顕著に見られます。
しかし、地域住民や企業にとって、最寄りの常磐道インターチェンジである谷和原ICおよび谷田部ICは利便性の課題を抱えていました。以下のような問題点が指摘されています:
- 最寄りのICまでの距離が長く、一般道の渋滞が発生しやすい
- 物流車両の流動性が低く、企業の拠点整備に支障をきたしている
- 地域の観光資源活用が進まない要因の一つとなっている
こうした課題を解決するために、新たなスマートICの設置が計画され、地域交通の円滑化を目指すこととなりました。
スムーズな運用を実現!つくばみらいスマートICの技術的な工夫

スマートインターチェンジの導入には、最新の交通管理技術が活用されています。特に、高速道路の出入口としての安全性や運用効率を最大限に高めるため、以下の技術的ポイントが考慮されています。
① ETC専用運用で待ち時間を大幅削減
スマートICは、ETC車載器を搭載した車両のみが利用可能となることで、料金収受の自動化を実現します。これにより、従来の料金所で発生する渋滞を解消し、スムーズな通行を実現します。
また、ETCゲートには以下の技術が導入されます:
- 高精度な車両認識センサーによる通行管理
- リアルタイムの通行履歴をクラウドで一元管理
- ゲート通過時の通信時間を最適化し、スムーズな処理を実現
② 安全を確保するためのインフラ設計
スマートICでは、車両が安全に進入・退出できるよう、一旦停止型の運用方式を採用します。これにより、合流時の事故リスクを低減することが可能です。
さらに、以下の技術が導入されます:
- IC進入時の速度超過を防ぐ可変式速度標識の設置
- 夜間や悪天候時の視認性を向上させるLED照明システム
- AIを活用した事故検知システムの導入により、異常発生時の迅速対応
③ 周辺道路とのシームレスな接続
スマートICを円滑に機能させるためには、周辺の一般道とのスムーズな接続が不可欠です。そのため、以下の技術が活用されます:
- 信号機の連動制御システムを導入し、IC周辺の渋滞を緩和
- スマート交差点技術を採用し、車両と歩行者の安全性を向上
- 交通流動データを活用したダイナミック経路案内システム
これらの施策により、スマートICの利用者がストレスなくスムーズに通行できる環境が整えられます。
スマートICの仕組みを徹底解説!
スマートICは、従来のインターチェンジとは異なり、以下のような先端技術によって運用が行われます。
自動車とインフラの連携
スマートICでは、V2X(Vehicle to Everything)通信を活用し、車両とICの間で情報をリアルタイムに交換する仕組みが導入されます。これにより、交通状況に応じた最適なルート案内が可能となります。
交通管理システムの高度化
最新のITS(高度交通システム)を活用し、IC周辺の交通状況をリアルタイムで監視。混雑が予測される場合には、可変情報板などを通じてドライバーに適切な情報を提供します。
AI活用による予測分析
AI技術を用いて、過去の交通データや天候情報を分析し、渋滞や事故発生リスクを事前に予測。これにより、スマートICの最適運用が可能となります。
まとめ:常磐道に新設、「つくばみらいスマートIC」が正式名称に決定!
- つくばみらいスマートインターチェンジの正式名称が2025年2月27日に決定。
- 地域の交通利便性向上と経済発展を目的に設置が進行中。
- ETC専用運用や安全確保のためのインフラ設計が施される。
- V2X通信、ITS、AI分析など最先端技術が活用される。
- つくばみらいスマートインターチェンジの開業日は、2025年2月現在の情報では明らかにされていない。
参考文献