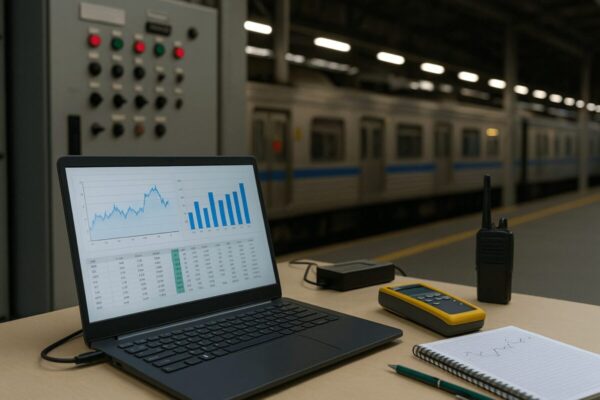- 自動車
- 公開日: 最終更新日:
ブロックチェーンによる運賃決済とは?将来の収益分配技術のアイデアを紹介!
株式会社MR.Nexus(エムアールネクサス)

Web3やデジタル通貨、スマートコントラクトといったキーワードが金融業界を中心に急速に浸透する中、公共交通分野でも「ブロックチェーン」の可能性が評価されています。特に、MaaS(Mobility as a Service)の発展に伴い、複数事業者間の収益分配や補助金の根拠データの透明化といったニーズが高まる今、公共交通業界にとっての「ブロックチェーン型決済インフラ」の実用化が現実味を帯びてきました。
本記事では、地方交通・MaaS・自治体補助制度など、公共交通を取り巻く複雑な構造の中で、ブロックチェーンが果たしうる役割を多角的な視点から整理します。
背景:なぜ公共交通にブロックチェーンが必要なのか
交通系ICカードの限界
SuicaやPASMOなどの交通系ICカードは、日常の移動を便利にした一方で、事業者間での収益分配や自治体への報告など「裏側の業務」は複雑化しています。特にMaaSが広がる中で、
- 「ひとつの乗車」で複数事業者が関与するケース
- 自治体補助対象の利用記録との整合性確保
- 外部プラットフォーム(MaaS事業者)との連携
といった複雑性が増し、既存の「閉じたシステム」では対応が難しくなりつつあります。
MaaSと収益分配のブラックボックス化
多様な交通サービスを一元的に利用可能にするMaaSは、利用者にとっては便利ですが、事業者間で「誰がどれだけ収益を得るべきか」の透明性は課題です。紙の乗車券や定額制アプリでは特にこの課題が顕著で、
- 運賃の分配基準が非公開
- 自治体からの補助金精算が困難
- 不公平な分配による事業者間の信頼悪化
といったリスクが存在しています。
自治体と補助金制度の変化
赤字交通に対する自治体補助金は、近年「定量的根拠に基づく補助」へとシフトしており、「どの区間で誰が使ったか」を正確にトレースするニーズが高まっています。しかし現行のICカード基盤ではデータ連携や透明性に限界があります。

会社名株式会社MR.Nexus(エムアールネクサス)
住所〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号 日本橋水野ビル7階
キャッチコピー公共交通に変革を、技術革新で次世代の安全と効率を
事業内容Mobility Nexus は、鉄道・航空をはじめとする公共交通業界における製品・技術・メーカー情報を整理・集約し、事業者とサプライヤをつなぐ情報プラットフォームです。技術の導入事例や製品比較を体系化し、事業者が現場視点で最適な選択を行える環境を構築しています。
本サイトは、公共交通業界での実務経験を持つエンジニアが監修しており、現場感覚と専門性を重視した中立的な構成を心がけています。
現在、製品情報の整理にご協力いただけるサプライヤ様からの情報提供を募集しています。特長や導入実績、保守体制などを詳細に記載します。製品個別単位での掲載、比較記事への参画など、目的に応じて柔軟に対応可能です。公共交通の技術導入を後押しする情報基盤づくりにぜひご協力ください。
関連記事
掲載に関する
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください