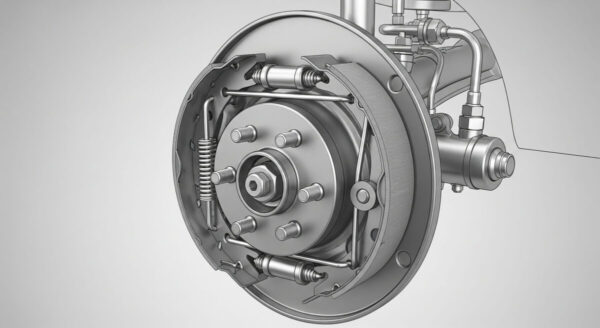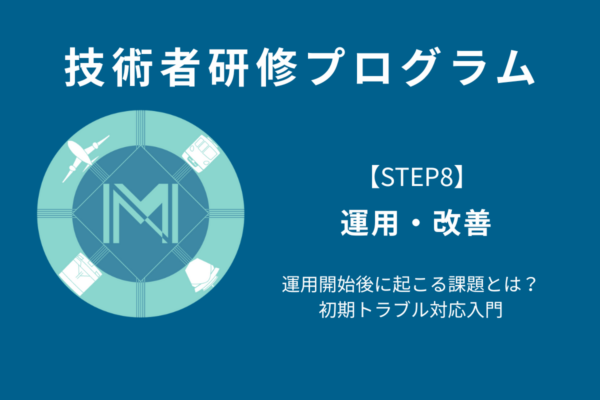公開日:
V2Xの対応車種を国内外メーカー別に紹介!将来の展望まで
- 自動車
- 用語解説

Mobility Nexus会員の3大特典!
-
👉
業界最前線の専門家による、ここでしか読めないオリジナルコンテンツを大幅に拡充!
-
👉
実践的なノウハウ、課題解決のヒントなど、実務に直結する学習コンテンツ
-
👉
メルマガ配信による、業界ニュースを定期購読できる!
V2X(Vehicle-to-Everything)は、車両が周囲のインフラや他の車両と通信し、リアルタイムで情報を交換する技術です。安全性の向上や効率的なエネルギー活用に大きな可能性を秘めており、エコで快適な社会の実現に欠かせない存在となっています。本記事では、国内外のV2X対応車種や関連製品、導入メリットなどについて詳しく解説します。
V2Xとは?V2Xの基本概念と導入のメリットを解説!

V2X対応車種とは、車両が周囲のインフラや他の車両と通信することで、リアルタイムに情報を交換できる機能を備えた車両を指します。これは車両同士の接触事故防止や緊急時の対応、渋滞回避といった安全面や利便性の向上を目的としており、現代のスマート交通システムの中で重要な役割を果たしています。V2X技術を活用することで、車両が道路や交通状況に適応しやすくなり、より効率的な運転体験が可能になります。加えて、V2Xは都市部の交通渋滞の緩和、エネルギー消費の削減、環境負荷の低減といった広範な効果も期待されています。
V2X技術の基本概念
V2Xとは「Vehicle to Everything」の略で、車両がさまざまな対象と通信してリアルタイムで情報を交換する技術を指します。具体的には、車両間通信(V2V)、インフラとの通信(V2I)、歩行者との通信(V2P)、ネットワークとの通信(V2N)を通じて、以下のような情報の共有と利活用が行われます:
V2V(車両間通信)
他の車両の速度、位置、方向といったデータを交換し、接触事故のリスクを低減します。急ブレーキや進路変更の際に周囲の車両に警告を送ることができ、ドライバーの反応を補完する役割も果たします。
V2I(インフラ通信)
信号機や道路標識、レーン変更の指示などインフラからの情報を受け取り、運転環境の変化に対応します。例えば、信号機との通信で赤信号の接近を警告したり、交通渋滞の情報を取得して経路を変更することが可能です。
V2P(歩行者通信)
歩行者や自転車利用者と通信し、周囲にいる歩行者の存在を検知することで、歩行者との衝突事故を防ぎます。特に見通しが悪い場所や交差点などでの安全性向上に寄与します。
V2N(ネットワーク通信)
インターネットやクラウドを介してリアルタイムで交通情報や天候情報を取得し、走行計画を最適化します。これにより、車両は道路状況や気象変化に柔軟に対応できるようになります。
V2X技術により、道路状況や他の車両の動きを的確に把握できるため、ドライバーはより安全で効率的な運転が可能となり、全体的な交通の安全性向上に大きく貢献します。さらに、将来的には自動運転技術とV2Xの連携により、完全な自動運転社会の実現にも寄与するとされています。
関連記事:V2X(Vehicle to Everything)とは?メーカーと対応車種や市場動向まで徹底解説!
V2X対応車種の導入メリット
V2X対応車種を導入することによって、交通のスムーズな流れや運転の安全性向上が期待でき、長期的には環境にも優しい効果が見込まれます。V2X技術がもたらす主なメリットは次の通りです:
交通渋滞の緩和
V2Xはリアルタイムで交通状況を把握するため、渋滞が発生しやすい場所を回避したり、最適な経路を提案することで、全体的な交通の流れをスムーズにします。これにより、特に都市部での移動時間の短縮が可能です。
事故の予防と安全性向上
V2Xにより、他の車両の動きや道路の変化を瞬時に検知し、ドライバーへ警告を発することで、追突事故や交差点での出会い頭の事故を防ぎます。特に、夜間や視界が悪い環境でも安全性を向上させます。
エネルギー効率の向上
V2Xは電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)と組み合わせることで、エネルギー消費を効率化します。例えば、家庭用電力として車両のバッテリーを使用したり、蓄電された電力を再生可能エネルギーとして利用することが可能です。これにより、家庭のエネルギー消費を低減し、環境負荷も軽減されます。
また、V2Xは災害時のバックアップ電源としても活用されるため、特に停電時に車両のバッテリーから家庭への電力供給を行うことができます。地域や家庭におけるエネルギー自給率の向上に寄与する技術としても期待されています。
V2Xシステム導入における課題
V2Xシステムの導入は多くのメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。これらの課題を解決することで、より広範にV2X技術が普及しやすくなるでしょう。代表的な課題は次の通りです:
インフラ整備とコスト負担
V2Xシステムは専用の通信インフラや機器が必要なため、導入には高額な初期コストが伴います。特に、広範囲での導入を進めるには公共および民間のインフラ投資が求められ、地方自治体や企業の連携が不可欠です。
サイバーセキュリティの確保
V2Xシステムは車両やインフラが相互に通信を行うため、サイバー攻撃のリスクが指摘されています。ハッキングによる情報漏洩や不正な車両制御を防ぐため、強固なセキュリティ対策が必要です。
通信インフラの整備と法規制
V2Xの普及には、通信ネットワークの整備が不可欠です。また、交通法規やプライバシー保護に関する法整備も必要であり、国や自治体が連携して新たな規制を策定する必要があります。
V2Xシステムの導入は多くの利益をもたらす可能性を秘めていますが、これらの課題を克服するためには、公共機関と民間企業が連携し、技術革新とインフラ整備を進めることが重要です。今後の普及に向けた取り組みが進む中で、さらなるコスト削減や法規制の整備、サイバーセキュリティの強化が期待されます。
V2X対応車種を主要自動車メーカー別にご紹介!トヨタ、日産、三菱、SUBARU、マツダなど

日本国内の主要自動車メーカーは、積極的にV2X対応車種の開発と導入を進めています。ここでは、各メーカーのV2X対応車種とその特徴について詳しくご紹介します。
トヨタのV2X対応車種
トヨタの代表的なV2X対応車種には、プリウスPHVとミライが挙げられます。プリウスPHVは、V2X技術によりスマートグリッドと連携し、蓄えた電力を家庭で使用できるシステムを提供しており、災害時にはバックアップ電源としても活用可能です。燃料電池車のミライも、V2X技術を活用して家庭や公共施設に電力を供給することができ、持続可能なエネルギー供給ソリューションとして注目されています。トヨタは、V2X技術を活用したエネルギーマネジメントを推進しており、車両を単なる移動手段だけでなく、家庭や地域のエネルギーインフラの一部とすることで、効率的な電力供給と消費の最適化を図っています。
日産のV2X対応車種
日産では、リーフとe-NV200が代表的なV2X対応車種です。リーフは、V2X技術を搭載した電気自動車(EV)で、車両から家庭やオフィスに電力供給が可能です。充電と放電を繰り返しながらエネルギーを効率的に管理することで、エコで持続可能なエネルギー利用が実現します。また、商用EVであるe-NV200も、家庭や事業所への電力供給を可能とし、特に非常用電源としても役立つため、商業分野での活用も期待されています。日産はV2X技術を活用し、EVと家庭やオフィス間での電力供給システムを構築することで、エネルギーの効率的な管理を目指しています。
三菱のV2X対応車種
三菱では、アウトランダーPHEVが代表的なV2X対応のプラグインハイブリッド車(PHEV)で、車両の電力を家庭やオフィスに供給する機能を備えています。エネルギーを効率的に使用することで災害時の電力確保にも役立ちます。同じくPHEVのエクリプスクロスも、V2X技術を活用して蓄電と放電のバランスを最適化し、家庭内エネルギーの消費をコントロールできます。三菱は車両の電力を家庭やビルに供給するシステムを提案しており、これにより家庭のエネルギー管理が効率化され、コスト削減にもつながります。
SUBARUのV2X対応車種
SUBARUのソルテラは、トヨタと共同開発した電気自動車で、V2X技術を活用した電力供給機能を搭載しています。家庭やオフィスへの電力供給も視野に入れて設計されており、日常のエネルギー消費を補助することができます。また、SUBARUはV2X技術を活用して安全性を強化する取り組みも行っており、V2V通信により他の車両と連携して事故リスクを低減し、運転支援機能の強化にも力を入れています。
マツダのV2X対応車種
マツダのMX-30 EVモデルもV2X技術に対応し、家庭での電力管理と連携することでエネルギーの最適利用を実現しています。特に、再生可能エネルギーを活用した持続可能な社会を目指しており、MX-30は家庭でのエネルギー供給を補助する車両として設計されています。マツダはV2X技術と再生可能エネルギーの利用を組み合わせ、効率的なエネルギー消費を可能にする戦略を推進しており、車両の電力を家庭や事業所で使用することでコスト削減と環境負荷の低減が期待されています。
まとめ:V2X対応車種を主要自動車メーカー別にご紹介!
| メーカー | 対応車種 | 特徴 |
|---|---|---|
| トヨタ | プリウスPHV | スマートグリッドと連携し、災害時のバックアップ電源としても利用可能 |
| トヨタ | ミライ | 水素燃料を利用した電力供給が可能で、持続可能なエネルギー供給に貢献 |
| 日産 | リーフ | 家庭やオフィスへの電力供給が可能で、エネルギー効率の最適化を実現 |
| 日産 | e-NV200 | 商用EVで、非常用電源としても利用可能。家庭や事業所への電力供給に対応 |
| 三菱 | アウトランダーPHEV | 車両の電力を家庭やオフィスに供給でき、災害時の電力確保にも役立つ |
| 三菱 | エクリプスクロスPHEV | 蓄電と放電を最適化し、家庭内エネルギーの消費を効率的にコントロール |
| SUBARU | ソルテラ | 家庭やオフィスへの電力供給が可能。V2V通信で安全性も強化 |
| マツダ | MX-30 EVモデル | 家庭での電力管理と連携し、再生可能エネルギーを活用したエコな運用を実現 |
V2X対応車種の海外メーカーをご紹介!BYD、ベンツ、MINIなど

海外メーカーもV2X対応車種の開発を進めており、各社が独自の技術で市場に挑戦しています。特に、中国のBYD、ドイツのメルセデス・ベンツ、イギリスのMINIは、それぞれ異なるアプローチでV2X技術を活用し、安全性やエネルギー効率の向上を目指しています。ここでは、注目の海外ブランドのV2X対応車種について詳しく解説します。
BYDのV2X対応車種
中国のEVメーカーであるBYDは、V2X技術においても先駆的な役割を果たしています。BYDの「ATTO 3」や「DOLPHIN」は、車両からの電力供給とエネルギー管理に重点を置き、家庭やビジネスシーンでの活用を視野に入れた設計が特徴です。これらの車種は、V2H(Vehicle to Home)やV2L(Vehicle to Load)に対応しており、家庭への電力供給が可能で、災害時の非常用電源としても活用できます。また、「DOLPHIN」には、最大1,500Wの電力で電化製品を使用できる「V2Lアダプター」もオプションで提供されています。BYDは政府や企業と連携し、V2Xインフラの整備にも積極的に取り組んでおり、中国国内でのV2X普及を推進しています。
ベンツのV2X対応車種
メルセデス・ベンツは、先進的な安全機能と共にV2X技術を搭載し、車両の安全性をさらに高めています。「EQS 450+」や「Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+」といったV2X対応モデルでは、ドライバー支援システムを強化するために、周囲の車両やインフラとのリアルタイム通信が可能です。これにより、交通事故のリスクが大幅に低減され、ドライバーと同乗者の安全性が向上します。また、V2Hに対応しており、車両から家庭への電力供給が可能です。ベンツは自動運転技術の重要な構成要素としてV2Xを位置づけ、今後の完全自動運転に向けた研究・開発を進めています。
MINIのV2X対応車種
MINIの「MINI Electric」は、都市部でのモビリティをサポートするためにV2X技術とエネルギー効率の向上に重点を置いています。この車種は、再生可能エネルギーとの連携が特徴であり、日中に太陽光発電などで得たエネルギーを蓄電し、夜間に家庭やオフィスで使用することが可能です。これにより、都市部でのエネルギー消費を抑え、二酸化炭素排出量を削減します。さらに、MINIはV2Xを通じて、交通渋滞の緩和や事故防止にも貢献しており、交通の流れをスムーズにすることで、効率的な都市モビリティを実現しています。「MINI Electric」は、小型車ならではの機動性と都市部での利便性を最大限に引き出すよう設計されており、エコ意識の高いユーザーに支持されています。
| メーカー | 対応車種 | 特徴 |
|---|---|---|
| BYD | ATTO 3 | V2HおよびV2Lに対応し、車両から家庭やビジネスシーンへの電力供給が可能。災害時の非常用電源としても活用できる設計。 |
| BYD | DOLPHIN | V2HおよびV2Lに対応し、車両から家庭やビジネスシーンへの電力供給が可能。最大1,500Wの電力で電化製品を使用できる「V2Lアダプター」をオプションで提供。 |
| メルセデス・ベンツ | EQS 450+ | V2Hに対応し、車両から家庭への電力供給が可能。先進的な安全機能とドライバー支援システムを強化し、交通事故のリスク低減と安全性向上に寄与。 |
| メルセデス・ベンツ | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | V2Hに対応し、車両から家庭への電力供給が可能。高性能モデルでありながら、エネルギー効率の向上と安全性を両立。 |
| MINI | MINI Electric | エネルギー効率の向上と再生可能エネルギーとの連携を重視。都市部でのモビリティをサポートし、環境負荷の低減に貢献。 |
V2Xシステム対応製品を徹底比較!オムロン、長州産業、パナソニックなど

V2Xシステム対応製品とは、V2X(Vehicle to Everything)技術を活用し、車両からの電力を家庭やビジネスシーンに供給したり、電力の双方向通信を行ったりするための製品です。これにより、電力の効率的な利用が可能になり、特に再生可能エネルギーの活用や、災害時の非常用電源としても役立つと期待されています。国内の主要なメーカーが提供するV2X対応製品には、それぞれ異なる特徴と強みがあります。ここでは、オムロン、長州産業、パナソニックのV2X対応製品について詳しく解説し、各製品の特長を比較します。
オムロンのV2X対応製品
オムロンは、V2X通信技術に強みを持つメーカーであり、電力の効率的な管理と安全な通信技術を提供しています。オムロンのV2X対応製品は、車両から家庭やオフィスへの電力供給をサポートし、リアルタイムでのエネルギー管理を可能にします。特に、独自のセンサー技術を組み合わせることで、精度の高い電力管理と安全性が確保されています。
オムロンのV2X製品には、家庭内でのエネルギー使用を最適化するためのシステムが備わっており、家電製品と連携して効率的な電力の供給と使用を実現します。また、エネルギー供給だけでなく、通信面でも高いセキュリティが確保されているため、サイバー攻撃や不正アクセスに対する強固な防御が可能です。これにより、家庭やオフィスで安心してV2X技術を活用できる設計になっています。
長州産業のV2X対応製品
長州産業は、太陽光発電と連携したV2Xシステムを提供し、家庭でのエネルギー自給自足を目指した製品を展開しています。同社のV2X対応製品は、車両からの電力供給と太陽光発電を組み合わせることで、持続可能なエネルギー利用を実現します。これにより、日中に太陽光で発電したエネルギーを夜間に家庭で活用でき、環境に配慮したエコな生活が可能です。
さらに、長州産業のV2Xシステムは、家庭内のエネルギー使用を最適化するだけでなく、災害時の非常用電源としても機能します。停電時には、車両に蓄えた電力や太陽光発電による電力を家庭に供給することで、生活を支えることができます。エコ意識の高いユーザーにとって、再生可能エネルギーとの組み合わせで環境負荷を抑えたエネルギー供給ができる点が大きな魅力です。
パナソニックのV2X対応製品
パナソニックは、高い技術力を持ち、車両と家庭間での電力供給を実現するV2X対応製品を提供しています。パナソニックの製品は、家庭と車両間での電力のやり取りを円滑に行えるよう設計されており、緊急時にはバックアップ電源として活用可能です。このため、災害時の停電時には車両からの電力を家庭に供給し、電化製品の動作を維持することができます。
また、パナソニックのV2Xシステムは多彩な用途に対応できる柔軟性が魅力であり、家庭用の電力供給だけでなく、オフィスや商業施設での利用にも適しています。さらに、エネルギー管理システム(EMS)との連携により、家庭内での電力消費をリアルタイムで監視し、最適化することが可能です。これにより、効率的なエネルギー使用が実現し、電力コストの削減にもつながります。
| メーカー | 特徴 | 主な機能 | 用途 | 強み |
|---|---|---|---|---|
| オムロン | V2X通信技術に強み、センサー技術との組み合わせで高精度な管理を実現 | ・家庭内の電力供給と最適化 ・安全な通信技術によるリアルタイム管理 |
・家庭やオフィスでの電力管理 ・車両からの電力供給 |
・サイバー攻撃対策が強力 ・安全で信頼性の高い電力管理 |
| 長州産業 | 太陽光発電との連携で持続可能なエネルギー供給を実現 | ・家庭内エネルギーの自給自足 ・災害時の非常用電源としても活用可能 |
・日中の太陽光発電と夜間利用 ・家庭でのエコな電力供給 |
・環境負荷を抑えたエネルギー管理 ・エコ意識の高いユーザーに支持される製品 |
| パナソニック | 高い技術力で多様な環境に対応、柔軟なエネルギー管理が可能 | ・家庭と車両間の電力供給 ・非常用電源としてのバックアップ機能 |
・家庭・オフィス・商業施設での利用 ・電力コスト削減と管理の効率化 |
・EMSとの連携でリアルタイム監視 ・災害時にも安定した電力供給が可能 |
V2Xシステムの施工・設置方法を解説!

V2Xシステムの導入には、車両やインフラとの接続、設置工事が必要です。適切な設置方法を理解することで、システムのパフォーマンスを最大限に発揮させることが可能です。
施工前の準備と確認事項
V2Xシステムの施工にあたり、まずは設置する場所や電力供給源の確認を行います。インフラ設備や車両側との通信環境も事前に整えておくことで、施工後のトラブルを防止できます。
V2X機器の設置方法
機器の設置には、車両のバッテリーと連携するためのインターフェースが必要です。また、通信モジュールをインフラ側に設置し、無線で情報をやり取りできるようにする必要があります。設置方法は製品によって異なるため、取扱説明書を確認し、専門業者に依頼することが推奨されます。
アプリとの連携と設定方法
多くのV2Xシステムは、スマートフォンやタブレットと連携して管理が可能です。専用アプリを通じて車両とインフラの接続状況を確認したり、エネルギーの使用状況をモニタリングできます。初回設定はアプリのインストール後に行い、通信が安定していることを確認します。
V2X対応車種の蓄電池を最大限に引き出す方法をご紹介!

V2X対応車種の蓄電池は、電力の蓄積と供給を効率化するために重要な役割を担っています。ここでは、蓄電池の効率を最大化する方法について解説します。
蓄電池の充電サイクルを最適化する
蓄電池の性能を長期間維持するためには、適切な充電サイクルを守ることが重要です。充電は完全に放電する前に行い、過充電や過放電を避けることで、寿命を延ばすことが可能です。
エネルギー管理システムとの連携
エネルギー管理システム(EMS)と連携することで、蓄電池の電力を効率的に管理できます。家庭やオフィスの電力使用状況を把握し、必要に応じて車両から電力供給を行うことで、エネルギーの最適化が実現します。
太陽光発電との併用によるエコな活用
太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、昼間に発電した電力を夜間に使用するなど、電力の自給自足が可能です。これにより、環境負荷を減らしながらエネルギーコストを削減できます。
V2X対応車種の費用対効果を見極める!導入後の削減コストを徹底解説!

V2X対応車種の導入には、車両の改造やインフラの設置など、一定の初期コストが必要ですが、長期的な視点で見ると費用対効果の面で多くのメリットがあります。V2X技術を導入することで、エネルギー効率の向上や電力コストの削減、さらには補助金や税制優遇の活用による投資回収が期待できます。ここでは、V2X対応車種を導入した際の費用対効果について、各観点から詳しく解説します。
導入コストとリターンの比較
V2Xシステムの導入には、車両の改造費やインフラ設置費といった初期投資が必要です。特に、専用の充電スタンドやV2X対応の通信システムを整えるための設備費用がかかります。また、車両自体にもV2X機能が搭載されている必要があり、通常の車両に比べて導入コストが高くなる傾向にあります。
一方で、V2X技術を活用することで、長期的には電力コストの削減効果が期待できます。車両に搭載された蓄電池を家庭やオフィスで活用することで、電気料金の削減が可能です。特に、夜間や電力料金が高い時間帯に家庭用電源として車両の電力を利用することで、電力コストを効率的に削減できます。加えて、導入にあたっては国や自治体の補助金や税制優遇措置も適用できる場合があり、これらを活用することで初期コストの負担を軽減することが可能です。
導入後の費用対効果を正確に把握するためには、投資回収期間(ROI)を見積もることが重要です。これは、V2X対応車両の導入による電力コスト削減効果や補助金などを考慮し、どれくらいの期間で初期投資が回収されるかを予測するものです。一般的には、エネルギー価格や使用頻度、補助金額によって回収期間は変動しますが、5年から10年で回収できるケースが多いとされています。導入を検討する際には、長期的な視点で判断することがポイントです。
電力コスト削減のメリット
V2X技術を活用することにより、車両の蓄電池に蓄えたエネルギーを家庭やオフィスで使用し、電力消費量を抑えることが可能です。これにより、月々の電気代を削減する効果が期待できます。特に、再生可能エネルギーが豊富な地域や、夜間電力を利用して車両に充電を行い、日中に家庭用電力として使用することで、大幅な電力コストの削減が見込めます。
また、V2X技術を活用することで、電力消費のピークシフトが可能となり、エネルギー需要の高い時間帯を避けて電力を供給することができます。これにより、電力会社からのピーク電力料金の適用を回避し、電力コストの負担を軽減します。さらに、災害時や停電時には、車両の蓄電池から家庭やオフィスに電力を供給することで、ライフラインの確保に貢献します。特に、電力供給が不安定な地域では、このようなバックアップ電源としての活用も大きなメリットです。
補助金や税制優遇の活用
V2X対応車両の導入にあたっては、国や地方自治体が提供する補助金や税制優遇措置を活用することが推奨されます。これにより、導入にかかる初期費用の一部を軽減でき、より手軽にV2X技術を導入することが可能です。多くの自治体では、エコカーの購入補助金制度や、再生可能エネルギーの利用促進に向けたインフラ整備補助金などが整備されており、V2X対応車両の購入やシステム導入時にこれらを利用できます。
また、税制面での優遇措置もあり、例えば、クリーンエネルギー車両に対する減税措置や、自家消費型のエネルギー設備に対する税制優遇が適用されることがあります。これにより、導入時の費用だけでなく、運用時のランニングコストに対しても減税効果が得られます。制度の内容や適用条件は地域や時期によって異なるため、最新の情報を自治体の公式ウェブサイトやエネルギー関連の助成金情報で確認し、賢く活用することが重要です。
このように、V2X対応車両の導入は初期コストがかかりますが、長期的な電力コスト削減効果や、補助金・税制優遇措置を活用することで費用対効果の高い選択肢となり得ます。エネルギーの有効活用と電力コストの削減、さらには補助金制度による費用軽減など、総合的に検討することで、より効率的な導入計画を立てましょう。
V2X対応車種の将来展望!今後の発展と活用のシナリオを解説!
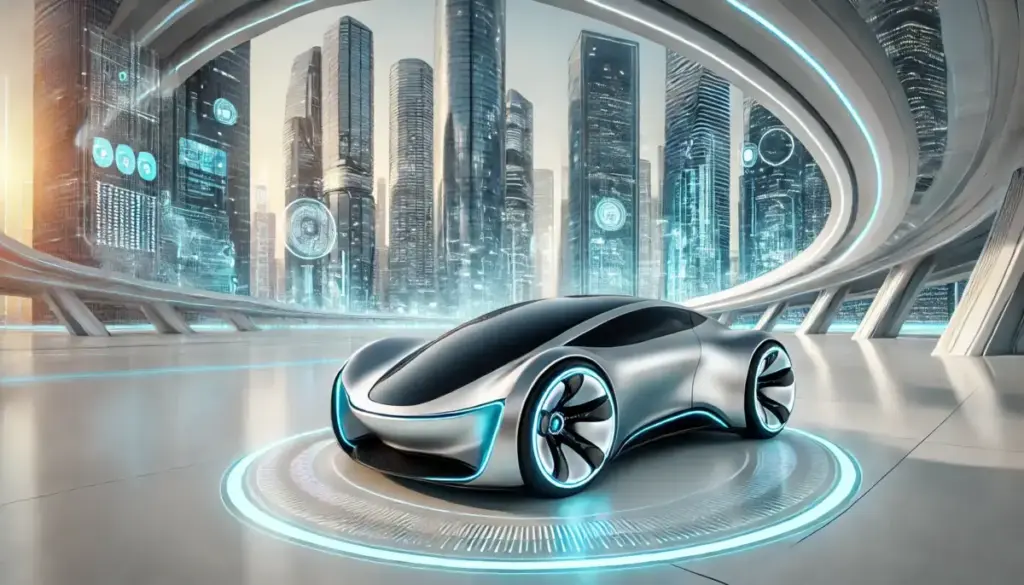
V2X技術は今後も進化し、さらに多くの分野で活用されることが期待されています。ここでは、V2X技術の将来展望と今後の利用シナリオについて解説します。
5G通信との連携による高精度な制御
5G通信技術の普及により、V2Xシステムの通信速度や信頼性が向上し、リアルタイムで高精度な制御が可能になります。これにより、スマートシティや自動運転技術への応用が期待されています。
スマートグリッドとの連携
V2X技術は、スマートグリッド技術と連携することで、再生可能エネルギーの効率的な活用が可能です。エネルギー管理の最適化により、持続可能な社会の実現に貢献します。
将来的な普及と市場の拡大
V2X対応車両の普及が進むことで、インフラ整備も進展し、より多くの消費者が恩恵を受けられるようになります。今後の市場拡大により、さらなる技術革新と価格の低下が期待されます。
【まとめ】V2Xの対応車種を国内外メーカー別に紹介!将来の展望まで
V2X技術の普及は、車両の安全性向上やエネルギーの効率的な利用に大きな影響を与えることが期待されています。国内外の主要メーカーによるV2X対応車種や関連システムの開発は日々進んでおり、将来のスマート社会に欠かせない技術として注目されています。
- V2X技術は車両とインフラ、他の車両、歩行者などとの通信を可能にし、安全性と利便性を向上させる
- 国内外の主要自動車メーカーがV2X対応車種を提供し、普及が進んでいる
- オムロン、長州産業、パナソニックなどの製品がV2X技術を支えている
- 導入に伴う費用対効果を考慮し、エネルギーコストの削減や補助金を活用できる
- 5Gやスマートグリッド技術との連携により、さらに多様な活用が期待される
関連記事
業界別タグ
最新記事
掲載に関する
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください