公開日: 最終更新日:
仮設設計・工事中安全管理の基礎知識
- 技術者研修
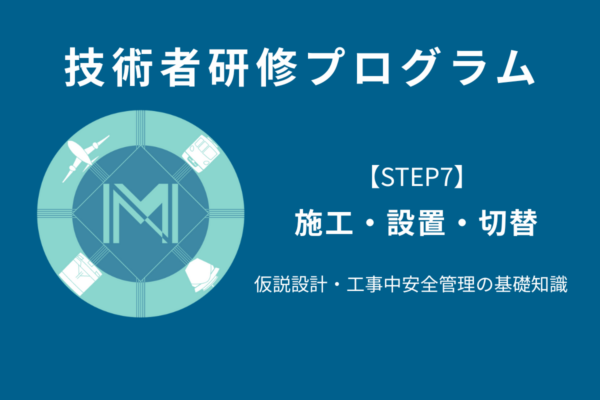
はじめに:仮設・工事中安全管理の役割とは何か
仮設設計や工事中の安全管理という言葉は、設計職や工事監督にとっては当たり前の用語ですが、入社して間もない技術者にとっては「本設のついで」「現場で都度調整するもの」として軽視されがちです。特に公共交通インフラの分野では、深夜・高電圧・狭隘な空間など、仮設段階こそ最もリスクが高く、計画と現場のすり合わせのズレが即座に事故や運行支障に繋がるという厳しい前提があります。
この章ではまず、「仮設設計・工事中安全管理とは何を目的とする業務か」を整理します。多くの若手技術者は、完成した設備や構造物を対象とした「本設の設計」「仕上がり品質」に目が行きがちですが、実際の工事プロセスにおいては、その手前の段階である仮設設計こそが、工事の円滑な進行と事故防止の鍵を握っています。
また、安全管理と聞くと、「安全帯の装着」「ヘルメットの着用」「作業手順書の作成」といった表面的なルールが想起されがちです。しかし本質的には、「どのようなリスクがどこに潜んでいるかを設計段階から予見し、それを排除・低減する」という、設計者・管理者・現場作業者が共通して持つべき思考に基づいています。
本記事では、仮設設計と工事中安全管理の基礎から実務への応用までを体系的に解説し、単なる「現場作業の段取り」ではなく、組織の中で確実に機能するべき技術領域として捉え直します。そして、現場の技術者が自ら思考し、設計や計画に意見を言えるようになることを目指します。
特に鉄道・空港・バスなどの公共交通インフラでは、一般の建設現場と異なり、「日常的に人が動き、稼働している中での施工」が求められます。そこでは仮設物や作業動線そのものが、利用者や他部門に影響を与えるインターフェースとなり、安全だけでなく顧客対応・現場の信頼性維持にも直結します。仮設・安全管理を単なる「現場任せ」にせず、設計・管理・教育の仕組みとして捉えなおすことが、今後の業界における人材育成・事故防止・技術継承の要となるのです。
第1章:仮設設計の基本概念と重要性
仮設設計とは、工事を安全かつ効率的に実施するために必要な「一時的な設備や構造物」を設計・計画する業務です。対象となるのは、足場や作業通路、仮囲い、仮設電源、仮設照明、搬入経路、作業員動線、保安柵、仮設看板など多岐にわたります。これらは完成後に撤去されることが前提であるため、本設の設計に比べて軽視されやすい傾向がありますが、実際には工事中の安全性と進行効率を大きく左右する極めて重要な要素です。
公共交通業界における仮設設計は特に重要です。たとえば鉄道では、終電から始発までの限られた作業時間の中で施工を完了しなければなりません。また、ホームや線路などの狭隘空間での作業が多く、仮設足場や作業帯が利用者や既設設備に与える影響を最小限にする必要があります。空港やバスターミナルでも、運行中の施設を維持しながら行う工事が多いため、仮設設計には「運用と工事の両立」という視点が不可欠です。
さらに、仮設設計では「人の動き」や「資機材の流れ」までを含めた立体的な空間設計が求められます。通行人・作業員・資材・重機がどのように交錯するか、どのタイミングでどこが混雑するかを予測し、それを避けるための計画を立てる必要があります。たとえば、材料を搬入するための仮設スロープをどこに設置するか、作業員の退避スペースをどこに設けるか、照明の当て方が作業環境や視認性にどのような影響を与えるか、といった点はすべて仮設設計の範疇です。
本設の設計が「最終成果物をどうつくるか」を目的とするのに対し、仮設設計は「その工事をどう安全に・段取りよく実行するか」に焦点を当てています。仮設をおろそかにすると、工程遅延・作業効率の低下・ヒヤリハット・重大事故といった問題が発生します。逆に言えば、しっかりとした仮設設計を行うことで、工事全体の質と安全性を高めることができます。
設計業務に携わる技術者は、「仮設は現場任せ」という思い込みを捨て、設計図面の中に仮設要素を織り込むべきです。現場の実態を知らなければ実践的な仮設設計はできませんが、一方で現場での経験を設計側にフィードバックしなければ、属人的な対応に留まってしまいます。これを防ぐには、部門間で仮設に関する情報を共有し、標準的な設計プロセスに組み込んでいく取り組みが必要です。
仮設設計は「一時的なもの」ですが、その安全性と合理性は、最終的に本設の品質やプロジェクト全体の信頼性に直結します。現場技術者としては、まずこの位置づけを正しく理解することが、工事における技術力・判断力を養う第一歩です。
第2章:工事中のリスクマネジメントと現場安全計画
工事現場では、日々状況が変化し、時間帯や工程の進み具合によってもリスクの種類と大きさは変動します。したがって、安全管理は「静的なルール遵守」だけでなく、「動的なリスク変化への対応力」が求められます。特に公共交通インフラの現場では、狭隘な場所で夜間に行われる作業が多く、転倒・感電・墜落・列車との接触・第三者被害など多様なリスクが常に存在しています。
リスクマネジメントとは、こうしたリスクを「予測→評価→対策→共有→監視」というサイクルで管理することです。初学者にとっては、リスクの“洗い出し”を甘く見がちですが、実務ではこの段階が最も重要です。現場での作業手順を頭の中でシミュレーションし、「どこでつまづくか」「どこに人が集中するか」「手が届かない箇所はないか」など、具体的なリスクを言語化・図示する能力が求められます。
現場で用いられる代表的な安全管理ツールには、以下のようなものがあります。
- KY(危険予知)活動: 作業前にチームで作業内容とリスクを共有する
- TBM(ツールボックスミーティング): 現場ごとに朝礼・夜礼形式での安全確認
- リスクアセスメント: 事前に想定される危険を評価し、対策を設計に反映
- 是正処置・事後レビュー: ヒヤリハットや事故後の分析と改善
ただし、これらのツールが形骸化している現場も少なくありません。例えば、形式的にKYシートを作成しても、リスクが具体的に記述されていなかったり、チームで共有されていなければ意味がありません。また、若手技術者が「これはおかしい」と感じても、それを現場で発言しにくい風土があると、潜在的なリスクが放置されることになります。
重要なのは、こうしたリスク管理活動を「現場の負担」ではなく、「工事全体を守る仕組み」として捉え直すことです。安全管理の目的は、「事故をゼロにすること」だけではなく、「事故を未然に防ぎながら工程を止めないこと」、すなわち“安全と工程の両立”にあります。設計段階から安全対策を組み込むことで、現場の負担を減らし、結果的に施工効率を高めることが可能になります。
また、工事中に発生するリスクは、現場だけで完結しないケースも多く見られます。たとえば、停電・通行止め・騒音・照明漏れなど、利用者や近隣への影響を伴う場合には、関係部門との事前調整や周知対応が不可欠です。こうした“非施工系の調整”を見落とすと、せっかく安全な工事をしても運行支障や苦情発生につながり、全体として失敗プロジェクトと見なされてしまいます。
現場技術者が担うべき役割は、単なる現地確認ではなく、事前のリスク洗い出しとその管理プロセスの旗振り役であるという認識が必要です。工事中の安全管理は、誰かの専任業務ではなく、設計者・管理者・現場責任者の全員が連携して実施すべき“チームの仕事”であることを、初学者の段階から意識づけることが、事故ゼロに近づく第一歩となります。
第3章:現場で使える仮設設計の実務ノウハウ
仮設設計は「理屈」よりも「実際に使えるか」が問われる領域です。設計図面上では正しく見えても、実際の現場では機材が搬入できない、人が通れない、照明が届かないといった事態が多々起こります。特に公共交通インフラの工事では、作業空間が限られており、他の部門との共用スペースや既存設備との干渉も多いため、「図面通りでは現場が回らない」場面にしばしば直面します。
まず、仮設設計の基本として押さえておきたいのは、「工事中のすべての人と物の動線を描き切ること」です。どこから資材を搬入し、どこに一時仮置きし、どこを通って作業員が現場入りするか。そして、それらがぶつからず、安全にすれ違えるスペースは確保できているかを、立体的に検討する必要があります。
以下に、現場で役立つ実践的な仮設設計のポイントを紹介します。
- 資材搬入ルート: 事前に現地確認し、最短かつ安全なルートを設定。大型機材や長尺物の回しやすさも確認。
- 作業帯の設定: 作業員の立ち位置、使用工具、退避方向を想定し、必要なスペースと安全確保を設計に反映。
- 仮設照明の配置: 夜間作業の多い現場では、照度分布を考慮して配置。影や眩しさの発生にも注意。
- 仮設電源・通信: どの機器をどこで使用するかを想定し、容量や配線ルートを明確化。感電対策も含める。
また、夜間短時間施工においては、「工事前の段取り=仮設の質」と言っても過言ではありません。たとえば、初日の段階で仮設通路が設置できなかった場合、その夜の作業すべてが滞ることもあります。したがって、「最初の1時間で仮設を立てられるか」が、工事の成否を分ける場面もあるのです。
このようなリスクを低減するには、「なるべく現場に合わせずに済む」仮設設計、すなわち事前の情報収集と標準化された計画が有効です。例えば、事前に構内図に仮設物の配置をレイヤー化して重ねておくことで、工程ごとの干渉が可視化され、設置・撤去の順序も整理できます。また、工事用の仮設備品をモジュール化し、事業所ごとにテンプレート化しておくことで、準備作業の属人性を排除することもできます。
さらに重要なのは、設計と現場の間に双方向のフィードバックループをつくることです。仮設計画がうまくいかなかった場合、「なぜ計画通りにできなかったか」を記録・分析し、それを次回の設計に反映させるサイクルが必要です。これには、現場技術者自身が仮設設計の視点を持ち、現場で感じた違和感や課題を積極的に上げていく文化の醸成も欠かせません。
つまり、仮設設計は「現場の自由裁量」で完結させるべきものではなく、「設計・管理・現場の知見を組み合わせて磨き上げていくべき設計対象」であると再認識する必要があります。現場で“使える設計”を実現するためには、実務の視点からの工夫と設計側の視座を両立させることが求められます。
第4章:部門連携と“仮設の責任者”の不在問題
仮設設計や工事中の安全管理は、単一の部門だけで完結する業務ではありません。実際の工事現場では、建築・電気・通信・設備・運輸など複数の部門が交錯し、それぞれの仮設や作業帯が重なり合っています。しかし現場では、「誰が全体を見ているのか」「他部門との干渉を誰が調整するのか」が曖昧になっていることが多く、これが重大事故や工程遅延の原因となっています。
典型的な例は、建築部門が設置した仮囲いが、電気部門のケーブルルートを塞いでしまうケースや、電気仮設盤の設置場所が設備機器の更新工事と干渉するケースです。それぞれの部門では自分たちの仮設は設計していても、「現場全体を俯瞰して統合的に調整する責任者」がいないため、干渉や不整合が現場で初めて発覚することになります。
このような問題が発生する背景には、以下のような構造的な課題があります。
- 工事発注単位が部門ごとに分割されている: 各部門が独自に計画・発注しており、仮設の共有設計がされない。
- 仮設に対する設計レビュー体制が不十分: 本設図面には厳しいレビューがあっても、仮設図面は口頭確認や現地調整任せになることが多い。
- 現場管理者が複数存在し、調整責任が曖昧: それぞれが“自分の範囲”は管理するが、全体調整は暗黙の了解で放置される。
こうした状況に対する改善策として、まず有効なのは「仮設設計統括者」の設置です。たとえば大規模工事や部門横断の更新プロジェクトにおいては、仮設設計・安全導線・仮設電源配置など、全体を俯瞰して設計・調整する専任者を一人置くことで、現場全体の整合性を担保できます。この役割は必ずしも専門職である必要はなく、「全体を俯瞰し、関係者に調整を促せる調整役」であればよいのです。
また、日常的な業務においても、仮設設計に関する定例会(仮設レビュー会)を実施し、各部門が自部門の仮設案を持ち寄って干渉箇所を確認する習慣づけが重要です。仮設図面をCAD上でレイヤー分けして重ね合わせたり、工程ごとの仮設物配置を3Dモデルで共有したりすることで、視覚的にも調整しやすい環境を整えることが可能です。
さらに、設計段階での図面チェックリストに「仮設同士の干渉確認」「仮設撤去と本設の切り替え手順の確認」「他部門との調整記録の有無」といった項目を組み込むことも、部門横断的な思考を定着させる有効な手段です。こうした取り組みが組織全体に定着すれば、仮設管理が“誰の仕事でもない”という状態を防ぎ、各部門が責任を持って設計・施工に関わる風土を醸成できます。
現場で事故やトラブルが発生した際、原因として表面化するのは「確認漏れ」や「意思疎通不足」といった言葉ですが、その背景にはこうした部門間調整の構造的な不在があります。仮設設計においても、「設計者と施工者」「各部門間」「管理者と現場」の連携が機能する体制をつくることが、真の意味での安全確保と工程管理につながるのです。
第5章:工事中安全管理を担う若手技術者の思考法
「安全第一」とはよく言われますが、実務においてはその言葉が形式的に使われがちです。安全帯の着用、ヘルメットの点検、作業前のKY活動…。これらは確かに重要ですが、単なる“儀式”として行われていては、本来の目的である事故の未然防止にはつながりません。特に若手技術者は、「安全対策とは何を考え、どのように判断し、どこに関わるべきか」という視点を持つことが重要です。
若手のうちから身につけておくべき思考の軸は、「安全は段取りの延長であり、設計の一部である」という認識です。安全対策は工事現場に入ってから考えるものではなく、設計段階、計画段階から組み込んでいくべきものです。たとえば仮設計画においても、「退避スペースをどこに確保するか」「夜間照明が作業帯全体に届くか」といった視点は、安全と施工効率の両方を担保する要素です。
また、若手技術者にありがちな落とし穴として、「ベテランが確認しているから大丈夫」「協力会社が手配するから任せてよい」という受け身の姿勢があります。現場においては、あらゆる情報が断片的に存在しており、「誰かが知っているはず」という油断がリスクを招きます。若手であっても、現場を歩いて気付いたこと、設計と違う点、不安に感じる点があれば、臆せず指摘する姿勢が重要です。
そのためには、若手自身が以下のような行動指針を持つとよいでしょう。
- 施工手順を紙上で追体験する: 作業者になったつもりで「ここで足が滑る」「ここで頭をぶつける」と想像する。
- 現場の“違和感”を記録に残す: 単なる気づきでもよいので写真・メモ・スケッチとして残し、共有する。
- 「何かあったとき」の想定を常に持つ: 仮に倒れても逃げられるか、非常時の退避動線は確保されているかを確認する。
- 仮設・安全の改善提案を自ら出す: 仮設通路の幅や照明の当て方など、気づいたことを提案する習慣を持つ。
また、上司や協力会社のベテランとの関係性においても、「教えてもらう」姿勢だけでなく「自分から問いかける」ことが信頼構築につながります。特に安全に関する話題は、上下関係を越えて共有されるべきものであり、若手の意見がベテランの見落としを救うこともあります。
さらに、若手が意識すべきもうひとつの視点は、「設計者としての目線を持つ」ことです。現場作業をする中で、「この設計では危ない」「ここに手すりが必要だ」といった気づきがあれば、それを現場対応で終わらせず、設計側へフィードバックすることで、次回以降の改善につながります。この“設計目線を持った現場力”こそが、若手技術者が5年以内に習得すべき力のひとつです。
現場における安全管理とは、ルールを守ることではなく、状況を読み取り、周囲と協力し、自ら考えて行動することです。そしてその出発点は、「自分の判断が安全を支えている」という実感を持つことにあります。初学者であっても、“安全を設計する技術者”の一員としての意識を育てていくことが、組織全体の安全文化を底上げする鍵となります。
第6章:仮設設計における標準化・再利用・教育設計
仮設設計は現場ごとに状況が異なるため、「その都度考えるもの」というイメージを持たれがちです。しかし、現実には似たような作業空間・同種の設備更新・反復的な施工条件が多数存在し、過去の仮設計画を活用することで、設計精度の向上・準備時間の短縮・安全性の平準化が実現可能です。属人化を防ぎ、若手技術者や外部委託先でも一定品質を確保できる仕組みが求められます。
まず、標準化に取り組む際に有効なのは、以下のような観点から仮設設計要素を分類・整理することです。
- 空間ごとの仮設構成: 駅構内、変電所、ピット内、ホーム上など、典型的な空間別にテンプレートを整備
- 作業種別のパターン化: ケーブル更新、機器交換、躯体補修など、作業内容ごとの仮設事例集を蓄積
- 安全対策のチェックリスト化: 滑落防止、感電防止、照度確保、導線管理などを定型項目として整備
これらのテンプレート化やチェックリスト化を進めるうえでは、「過去の事故・ヒヤリハット事例」を含めたレビューが重要です。単に“うまくいった例”を蓄積するだけでなく、“失敗した設計や想定外の事象”も含めて体系化することで、実務での判断材料として活きたナレッジとなります。
さらに、仮設設計の標準化は教育分野とも深く結びついています。特に若手技術者や設計補助者にとって、最初から自由に設計を任されても正解がわからず、場当たり的な対応になりがちです。そこで、教育ツールとして以下のような資源を整備することが有効です。
- 仮設設計演習教材: 過去の図面や施工写真を使った“仮設配置計画の検討ワーク”
- 工程シミュレーション動画: 3Dモデルやタイムラプスを用いた段取り解説
- OJT連動チェックリスト: 現場見学や立会時に確認すべき視点を整理した携帯用ツール
また、教育を“単発の研修”で終わらせず、工事後のレビューを組織学習へと還元することも欠かせません。たとえば、工事完了後に仮設計画と実際の施工内容を比較し、「どこがうまくいったか」「改善点は何か」を定例報告として残すことで、設計部門や次回以降の担当者に活かすことができます。
加えて、仮設設計に関する情報共有の仕組みも重要です。社内イントラ上に仮設設計の事例ライブラリを整備したり、プロジェクト単位で使用した図面・写真・是正記録を定型化して保存したりすることで、組織としての技術資産が蓄積されていきます。これにより、個人の経験ではなく、チーム・会社全体としての「仮設の技術力」を高めることができます。
仮設設計は、工事が終われば消えてしまう“儚い設計”ですが、その積み重ねと標準化が、組織全体の安全文化・技術継承・教育効果を飛躍的に高めることにつながります。形式だけでなく、実務に役立つ仕組みとして設計・運用・教育を一体化させる取り組みが、次世代の現場力を支えていくのです。
第7章:仮設・工事中安全の観点を設計・更新プロセスに埋め込む
仮設設計や工事中安全管理を単発の対応ではなく、事業者全体の「設計・更新プロセス」の一部として制度的に組み込んでいくことが重要です。特に、Mobility Nexusで定義する8ステップ(課題認識〜運用開始)を活用すれば、技術導入や設備更新における安全配慮が“誰かの意識頼み”にとどまらず、構造的に保証される仕組みを構築できます。
以下では、8つのステップそれぞれにおける仮設・安全管理の観点を整理します。
- STEP1:課題認識・ニーズ抽出
過去に発生した施工中事故やヒヤリハットを振り返り、「仮設に起因した課題」がなかったかを明確にする。 - STEP2:技術調査・ソリューション探索
製品・工法・工程案を検討する際に、仮設条件や施工上の安全確保に支障がないかを初期段階から確認する。 - STEP3:要件定義・仕様検討
「施工時に退避スペースが確保できること」「深夜帯の工事にも対応できること」など、安全上の要件を仕様書に記載する。 - STEP4:開発・設計・調達
実施設計において仮設計画を反映させる。複数部門の仮設が重なる場合は、設計レビューでの仮設統括確認を必須とする。 - STEP5:試験・検証・現場適合性評価
仮設構造物や導線の寸法・強度・視認性が現地条件に適合しているか、施工前に現場での確認・モックアップを行う。 - STEP6:導入決定・契約・スケジュール策定
工事計画書に仮設設計図・安全対策一覧を添付。委託契約時には、施工者に対して仮設管理義務を明記する。 - STEP7:施工・設置・切替作業
各工期の立ち上がり時に仮設状態をチェック。工程と安全が両立しているか、現場管理者による巡視・是正体制を整備する。 - STEP8:運用開始・フォローアップ・継続改善
工事完了後に仮設設計・工事中の安全管理についてレビューを実施。成功事例・失敗事例を技術資料としてナレッジ化する。
このように、仮設・安全の視点を各フェーズで明示的に位置づけることで、属人化を防ぎ、組織として一貫した安全設計思想を持つことができます。また、発注側としても、ベンダーや施工者に対して「安全配慮型の設計・段取り」を求める基準が明確となり、技術導入全体の質が高まります。
とくに、委託業務においては「設計は自社、施工は外部」となるケースが多く、責任の所在が曖昧になりやすい領域です。そのため、仕様書や委託条件に「仮設計画の事前提出義務」「施工中安全対策の報告義務」を明文化することが、事故予防につながります。外注の安全を“信頼”で済ませず、“仕組み”で確保する意識が欠かせません。
また、予算・工程の見積もり段階で「安全対策・仮設計計上」が抜け落ちることも多いため、予算化の標準項目に「仮設・安全・現場管理費」を明示しておくことも、設計プロセスにおける実効的な改善手段です。
最終的には、仮設や安全の配慮が“本設の外側”ではなく“設計の内側”にあることを、プロジェクト全体で認識しなければなりません。安全を別業務とせず、技術導入の一部として捉える。その思考の切り替えこそが、業界全体のレベルアップに直結するのです。
まとめ
仮設設計・工事中の安全管理は、「一時的なもの」「現場任せのもの」として軽視されがちですが、実際には設計・工程・安全・教育のすべてにまたがる極めて本質的な業務です。本記事では、現場の実態に即した実務的な観点から、若手技術者が理解・実践すべき基礎知識を整理しました。最後に要点を振り返ります。
- 仮設設計は「工事を成立させる前提条件」であり、本設設計と同等の計画性が求められる。
- 安全管理は現場でのルール遵守ではなく、設計段階からの段取り・空間設計に根ざした取り組みである。
- 仮設・安全を“誰の責任か不明”な領域にせず、部門横断で調整・統括する役割と仕組みが必要である。
- 若手技術者こそ「仮設の目」で現場を見る視点」を養い、設計・現場の両側面から安全を設計する意識を持つべきである。
- 標準化・教育設計・ナレッジ化を通じて、仮設・安全の実務知見を組織全体の力として再利用・継承することが重要である。
仮設設計と安全管理の視点を、業務の付随事項ではなく、「工事を成功に導く設計そのもの」として再定義することが、公共交通インフラの持続的な安全性と施工品質の礎になります。次世代の現場力を高める第一歩として、今日から自らの設計や現場対応を見直してみてはいかがでしょうか。
振り返りワーク
この記事で学んだ内容を、自身の理解として定着させるためには、アウトプットが欠かせません。以下の設問を通じて、知識の確認だけでなく、業務や教育の現場でどう活かせるか、自分の立場に置き換えて考えてみてください。思考を言語化することが、現場での判断力や後輩への指導力にもつながります。
Q1:仮設設計や安全管理は、工事設計の一部として計画的に組み込むべき業務である。
- Yes
- No
Q2:次のうち、仮設設計に関する説明として誤っているものを1つ選びなさい。
- A. 仮設は施工が終われば撤去されるため、設計段階では検討の優先度が低い。
- B. 仮設設計には作業動線や資材搬入経路も含まれる。
- C. 仮設物の干渉は、複数部門での事前調整が必要となる。
- D. 工事の円滑化と安全性を確保するうえで、仮設設計は極めて重要である。
Q3:次のうち、現場での仮設設計レビューにおいて最も実務的な行動はどれか。
- A. 設計図面の範囲内での安全対策がとられていれば問題ないと判断する。
- B. 現場での導線や人・物の動きを具体的にシミュレーションする。
- C. 施工者に一任し、自部門の仮設管理に専念する。
Q4:次のA〜Cのうち、「若手技術者が現場安全を自分ごととして捉える」表現として最も適切なものを選びなさい。
- A. ベテランが確認するので、若手は報告内容だけ覚えておけばよい。
- B. 設計通りかどうかではなく、「これで本当に安全か」を現場目線で見直す。
- C. 現場では気になることがあっても、まずは黙って様子を見る。
Q5:以下の工程を、工事中の仮設設計における実施順に並べ替えなさい。
- A. 図面に仮設物の配置と導線を反映する
- B. 現地条件を踏まえて仮設構成を検討する
- C. 設計レビューで他部門との干渉を確認する
Q6:あなたの担当現場において、「仮設計画の標準化と再利用」を実現するために、まず取り組めそうなことを1つ記述してください。
- 【記述欄】
Q7:入社2年目の後輩が「安全対策は施工者の仕事だと思っていました」と言ったとき、あなたはどう答えますか?指導者としての視点で、簡潔に助言してください。
- 【記述欄】
関連記事
業界別タグ
最新記事
掲載に関する
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください














