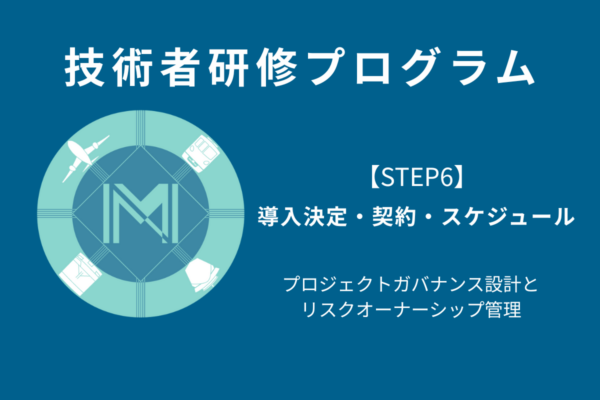公開日:
工事リスクマネジメント(リスク登録簿活用法)
- 技術者研修

1. 工事リスクマネジメントとは何か ― 現場で起きる「想定外」を減らす思考法
公共交通の工事現場では、「想定外」は必ず起きるものとして扱われます。運行に支障をきたす事故、地下構造物との干渉、夜間作業の遅延、設計条件の齟齬──これらはすべて、事前に兆候をつかめていれば回避できたケースが多いのが実情です。リスクマネジメントとは、そうした「想定外」を体系的に減らし、影響を最小限に抑えるための仕組みです。単なる安全管理の延長ではなく、技術導入・設計変更・工期短縮など、プロジェクト全体の質を支える基盤として位置づけられます。
工事におけるリスクは、現場で顕在化しますが、その多くは管理部門の段階で生まれています。設計仕様の不整合、契約スコープの認識ずれ、調達スケジュールの遅延など、上流での判断が後工程に波及する構造があるためです。つまり「リスクの源流は図面や会議にある」という認識を持つことが、現場リスクの第一歩です。現場での“頑張り”だけでは解決できないリスクは、そもそも管理の構造で予防する必要があります。
リスクマネジメントを実効性あるものにするには、感覚的な危機意識ではなく「リスクの見える化」が欠かせません。そこで活用されるのがリスク登録簿(リスクレジスター)です。これは、発生し得るリスクを体系的に洗い出し、その原因・影響・対応策・責任者を一覧化する管理台帳であり、工事進行中に随時更新する「生きた記録」として機能します。形式的に提出して終わる書類ではなく、判断・報告・教育に活用する運用型ツールとして捉えることが重要です。
リスク登録簿を導入すると、現場と管理部門の間に「共通言語」が生まれます。たとえば、「作業遅延の懸念」という曖昧な表現を「仮設搬入経路の確定遅延による夜間1時間短縮リスク」と明文化すれば、調達部門や列車運行管理者も具体的に議論できます。つまり、リスクマネジメントは“感覚の翻訳作業”でもあります。現場の直感を言語化し、管理側の判断を現場で再解釈できるようにする。この往復が、組織としての成熟度を高めます。
また、リスクを「排除すべきもの」とだけ捉えるのではなく、「制御可能な不確実性」として扱う姿勢も重要です。施工環境は日々変化するため、全てのリスクをゼロにすることは不可能です。しかし、リスクを事前に把握し、対応策を準備しておくことで、「発生しても致命傷にならない」状態をつくることができます。これは、安全文化と同様に、組織的学習の積み重ねによって形成される能力です。
初学者にとっては、リスクマネジメントは「管理職の仕事」に見えがちです。しかし実際には、最も重要な情報を持つのは現場の担当者です。日々の作業記録や小さな違和感の積み重ねこそが、将来の重大リスクを予防する鍵になります。本稿では、リスク登録簿を活用して現場と管理の知見を接続し、施工フェーズにおけるリスクを実務的に制御する方法を学びます。
関連記事
業界別タグ
最新記事
掲載に関する
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください