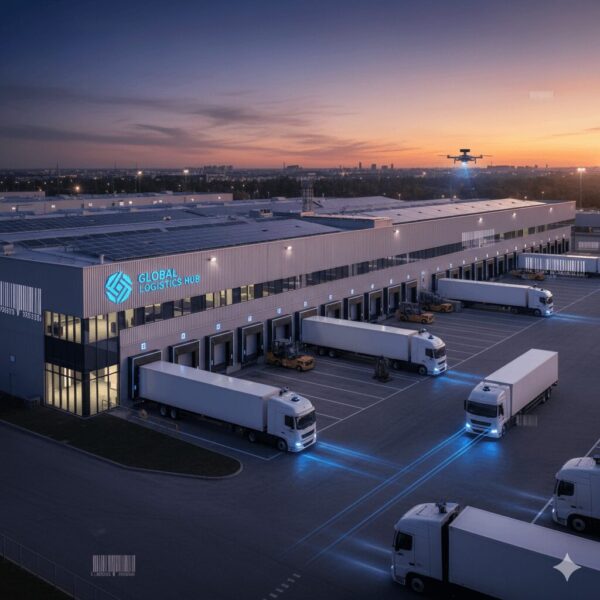公開日:
TMS(輸送管理システム)とは|物流用語を初心者にも分かりやすく解説
- 物流
- 用語解説

TMSとは、「Transportation Management System」の略で、日本語では「輸送管理システム」と呼ばれます。簡単に言えば、荷物の集荷から配送までの物流プロセス全体を効率的に管理するためのITシステムです。
「業界人だけど、いまいち言葉の意味が曖昧で…」「これから物流の仕事に携わるので基本的なことを知りたい」「自分の会社の業務効率をもっと改善したい」といったお悩みをお持ちではありませんか?
この記事では、TMSの基本的な概念から、その多様な機能、導入することのメリット、そして実際にどのような企業がどのように活用しているのかまで、専門家が初心者にもわかりやすく、丁寧に解説します。この記事を読めば、TMSの全体像が掴め、業務改善のヒントが見つかるはずです。ぜひ最後までお読みください。
TMS(輸送管理システム)とは何か?
TMSは、サプライチェーン全体を最適化するために不可欠なシステムです。物流の複雑なプロセスをデジタルで一元管理することで、コスト削減、サービス品質の向上、そして持続可能な物流の実現を目指します。では、具体的にどのような概念なのでしょうか。
物流業界におけるTMSの役割
TMSの最も重要な役割は、物流の「見える化」と「最適化」です。従来、電話やFAX、手書き伝票で行われていた配車計画、運行管理、進捗確認といった業務は、非効率で属人化しやすく、ミスも起こりがちでした。TMSを導入することで、これらの情報をシステム上で一元管理し、リアルタイムで共有することが可能になります。これにより、業務の透明性が高まり、問題発生時の迅速な対応や、より効率的な計画立案が可能になるのです。
TMSとWMS、OMSとの違い
物流にはTMS以外にも、WMSやOMSといった略語がよく登場します。これらはそれぞれ異なる役割を担っています。
- TMS(輸送管理システム):輸送を管理するシステムです。倉庫から荷物が出た後の、配車計画、配送ルート最適化、運行中の車両追跡などを担当します。
- WMS(倉庫管理システム):倉庫内を管理するシステムです。商品の入庫、在庫管理、ピッキング、梱包、出庫といった倉庫内の作業を効率化します。
- OMS(受注管理システム):受注を管理するシステムです。顧客からの注文を受け付け、在庫確認、出荷指示、請求処理など、注文から出荷までの事務作業を管理します。
これら3つのシステムは連携することで、注文から顧客への配送まで、一貫したサプライチェーンを構築します。特に、TMSとWMSは密接に関係しており、両方を導入することで物流全体の最適化が進みます。
TMS(輸送管理システム)の主要な機能と業務フロー
TMSは多岐にわたる機能を備えており、企業のニーズに応じてカスタマイズが可能です。ここでは、一般的なTMSが持つ主要な機能と、それが物流業務のどの部分を担うのかを具体的に見ていきましょう。
配車計画・運行計画の最適化
TMSの核となる機能の一つが、配車計画の自動化と最適化です。従来の属人的な配車計画では、個々のドライバーの経験や勘に頼ることが多く、非効率なルートや積載率の低い配車になりがちでした。TMSは、以下の情報を基に最適な配車計画を自動で立案します。
- 配送先、荷物の種類、数量、指定時間
- 車両の種類、積載可能量、積載可能容積
- ドライバーの勤務時間、休憩時間、スキル
- 道路状況、交通規制、通行料
これらのデータを分析し、最も効率的でコストの低いルートや配車を瞬時に導き出します。これにより、燃料費の削減やCO2排出量の削減にも貢献します。
リアルタイムでの車両追跡と運行管理
配送中の車両の位置情報をリアルタイムで把握できる機能もTMSの重要な要素です。GPSやIoTデバイスを活用することで、地図上に車両の位置が表示され、以下のことが可能になります。
- 進捗状況の可視化:荷主や顧客からの問い合わせに対し、正確な到着予定時刻を伝えることができます。
- トラブル時の迅速な対応:渋滞や事故、車両故障などのトラブルが発生した場合でも、リアルタイムで状況を把握し、別の車両を手配するなどの迅速な対応が可能です。
- 安全管理の強化:ドライバーの急ブレーキや速度超過などの運転データを収集し、安全運転指導に役立てることができます。
運賃計算と請求処理の自動化
運送業務では、複雑な運賃計算や請求処理が発生します。TMSは、契約に基づいた運賃や、走行距離、時間、荷物の種類などを基に、正確な運賃を自動で計算します。これにより、請求書の作成作業が大幅に効率化され、人的ミスの削減につながります。また、運送費の実績データを蓄積することで、運送コストの分析や、今後の運賃交渉の材料としても活用できます。
輸配送業務の進捗管理
配送状況は、荷主や顧客、そして自社の営業担当者にとって重要な情報です。TMSは、以下のステップで進捗管理を可能にします。
- 集荷:ドライバーが荷物を集荷した際に、システム上でステータスを更新。
- 配送中:GPS情報をもとに、現在位置や到着予定時刻をリアルタイムで表示。
- 配達完了:受領書をデジタルで取得(電子サインや写真など)し、配達完了を記録。
これにより、電話やFAXでの確認作業が不要となり、業務効率が飛躍的に向上します。
TMS(輸送管理システム)導入のメリット・デメリット
TMSは多くのメリットをもたらしますが、導入にあたって考慮すべきデメリットも存在します。導入を検討する際は、これらの点を総合的に判断することが重要です。
TMS導入で得られる6つのメリット
1. コスト削減と利益率の向上
TMS導入の最大のメリットの一つは、コスト削減です。配車計画の最適化により、無駄な走行距離が減少し、燃料費が削減されます。また、積載率の向上は、より少ない車両台数で多くの荷物を運べるようになり、車両の維持費や人件費の削減にもつながります。さらに、運賃計算や請求処理の自動化は、事務作業の効率化と人的ミスの削減を実現し、間接的なコスト削減に貢献します。
2. 業務効率化と生産性向上
手作業で行っていた配車計画や、電話での進捗確認、手書き伝票の処理といった煩雑な業務が自動化・デジタル化されることで、担当者の業務負担が大幅に軽減されます。これにより、担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、企業全体の生産性が向上します。ペーパーレス化も進み、情報の検索や共有も容易になります。
3. サービス品質の向上
リアルタイムでの車両追跡は、顧客への正確な到着予定時刻の連絡を可能にします。これにより、顧客の満足度が向上します。また、イレギュラーな事態が発生した際にも迅速に対応できるため、サービスの信頼性が高まります。配達完了の電子サイン機能は、誤配や荷物の紛失といったトラブル防止にもつながり、クレーム対応の時間とコストを削減します。
4. 労働環境の改善と人材確保
属人的な配車計画や長時間労働が常態化している運送業界では、労働環境の改善は喫緊の課題です。TMSは、最適なルートを提示することでドライバーの負担を軽減し、労働時間の適正化を支援します。これにより、ドライバーの離職率低下や、新たな人材の確保にもつながります。ブラックボックス化していた業務が可視化されることで、公平な評価制度の導入も可能になります。
5. データ活用による経営改善
TMSは、配車実績、走行距離、燃料消費量、運賃、ドライバーの稼働状況など、膨大なデータを蓄積します。これらのデータを分析することで、どのルートが非効率か、どのドライバーの生産性が高いかといった経営判断に役立つ情報を得ることができます。データに基づいたPDCAサイクルを回すことで、持続的な業務改善が可能になります。
6. 法令遵守(コンプライアンス)の強化
運送業界では、労働時間規制や安全運転管理に関する法令遵守が非常に重要です。TMSは、ドライバーの走行時間や休憩時間を自動で記録・管理し、過剰な労働や無理な運行を未然に防ぐことができます。これにより、企業のコンプライアンス意識を高め、社会的な信頼性を向上させることができます。
TMS導入のデメリット・注意点
メリットが多い一方で、導入にはデメリットも存在します。
- 初期費用とランニングコスト:高機能なシステムほど、導入費用が高額になります。また、月額の利用料や保守費用も発生します。
- 導入・運用までの時間と手間:システムの選定から導入、従業員の教育、既存業務との連携まで、時間と労力がかかります。
- 従業員の抵抗:新しいシステムへの移行は、従業員にとって負担となることがあります。導入目的やメリットを十分に説明し、理解を得ることが不可欠です。
TMS(輸送管理システム)の選定ポイント
実際にTMSを導入する際には、いくつかの重要なポイントがあります。適切なシステムを選び、スムーズに導入するために、以下の点を参考にしてください。
TMS選定の6つのポイント
数多くのTMSの中から自社に最適なものを選ぶために、以下のポイントを確認しましょう。
- 機能:自社の課題を解決するための機能が備わっているか。特に重要なのは、配車最適化、車両追跡、運賃計算、そしてWMSや基幹システムとの連携機能です。
- 操作性:現場のドライバーや配車担当者が直感的に使えるか。特に、スマートフォンのアプリ対応は重要です。
- 導入形態:クラウド型(SaaS)か、オンプレミス型か。クラウド型は初期費用を抑えられ、どこからでもアクセスできる利点があります。
- カスタマイズ性:自社の独自の業務フローに合わせてカスタマイズが可能か。パッケージ製品でも、設定変更で柔軟に対応できるかがポイントです。
- サポート体制:導入後のサポートや保守体制が充実しているか。トラブル時の対応や、アップデートの頻度も確認しましょう。
- 費用対効果:導入費用と得られるメリットを比較し、コストに見合う効果が期待できるか。複数のベンダーから見積もりを取り、総合的に判断します。
TMS(輸送管理システム)の最新動向と将来展望
技術の進化とともに、TMSも日々進化しています。ここでは、今後のTMSがどうなっていくのか、最新のトレンドを解説します。
AI・機械学習による予測と最適化の高度化
現在のTMSは、既存のデータに基づいて最適化を行いますが、将来的にはAIや機械学習を活用した「予測型」のTMSが主流になると考えられています。過去の交通情報、天候データ、季節要因などをAIが学習し、将来の渋滞や需要を予測することで、より精度の高い配車計画やルート最適化が可能になります。
IoTとの連携によるリアルタイムデータの活用
車両に搭載されたIoTデバイスやセンサーから、燃料消費量、タイヤの空気圧、エンジンの状態といった運行データをリアルタイムで取得し、TMSと連携させます。これにより、予知保全(故障が起こる前にメンテナンスを行うこと)が可能になり、車両のダウンタイムを最小限に抑えられます。
サプライチェーン全体の最適化へ
これまでのTMSは、主に輸送の部分に特化していましたが、今後はWMSやOMS、さらには生産管理システムなど、サプライチェーン全体のシステムと密に連携し、全体を最適化するプラットフォームへと進化していくでしょう。これにより、物流だけでなく、生産から販売までの全工程を統合的に管理することが可能になります。
TMS(輸送管理システム)導入成功事例と効果
実際にTMSを導入した企業は、どのような効果を上げているのでしょうか。ここでは、具体的な成功事例をいくつかご紹介します。
成功事例1:大手食品メーカーの事例
導入前の課題
全国に拠点を持ち、多数の協力運送会社に配送を委託していましたが、配車計画は担当者の経験に頼っており、特定の運送会社に負担が偏ったり、非効率なルートが散見されました。また、運送費の適正化も課題となっていました。
TMS導入後の効果
- 年間10%の運送費削減:TMSによる配車最適化で、積載率が平均15%向上し、走行距離が短縮されました。
- 配車業務時間の50%削減:属人化していた配車計画が自動化され、担当者の作業時間が大幅に短縮されました。これにより、他の業務に時間を充てられるようになりました。
- 運送会社との関係改善:データに基づいた公平な配車が可能となり、運送会社ごとの負担の偏りが解消されました。
成功事例2:中堅運送会社の事例
導入前の課題
ドライバーの高齢化が進み、長年の経験を持つベテランドライバーに業務が集中していました。属人化を解消し、若いドライバーでも効率的に業務をこなせる仕組みづくりが求められていました。
TMS導入後の効果
- 新人ドライバーの即戦力化:TMSが最適なルートを提示するため、地理に不慣れな新人ドライバーでも効率よく配送できるようになりました。
- 労働時間の適正化:システムが走行時間や休憩時間を管理することで、過剰な労働を自動で検知し、改善を促すことができました。
- 顧客満足度の向上:リアルタイム追跡機能により、顧客からの配送状況に関する問い合わせに即座に対応できるようになり、顧客からの信頼が向上しました。
TMSの導入形態と料金体系
TMSを導入する際には、その提供形態や料金体系を理解することが重要です。自社のビジネスモデルや予算に合った選択が求められます。
クラウド型(SaaS)とオンプレミス型
TMSには大きく分けて2つの導入形態があります。
- クラウド型(SaaS):ベンダーが提供するサーバー上のシステムをインターネット経由で利用する形式です。初期費用を抑えられ、導入がスピーディな点が大きなメリットです。定期的な月額・年額の利用料が発生します。サーバー管理やシステムアップデートはベンダーが行うため、自社での運用管理の手間が少ないのが特徴です。
- オンプレミス型:自社のサーバーにシステムをインストールして利用する形式です。初期費用が高額になりますが、一度導入すれば月額費用は発生しない場合が多く、長期的なコストを抑えられる可能性があります。自社の既存システムとの連携が容易で、高度なカスタマイズが可能な点もメリットです。
料金体系の種類
料金体系はベンダーによって異なりますが、主に以下のタイプがあります。
- ユーザー数課金:利用するユーザーの数に応じて料金が決まるタイプ。
- 車両台数課金:管理する車両の台数に応じて料金が決まるタイプ。
- 機能別課金:基本機能に加え、必要なオプション機能を追加するごとに料金が発生するタイプ。
- 従量課金:利用量(配車件数など)に応じて料金が決まるタイプ。
自社の事業規模や業務内容に最も適した料金体系を選ぶことが、コストを最適化する鍵となります。
TMSの技術的な仕組みとシステム連携
TMSがどのようにして高度な管理を実現しているのか、その技術的な側面を掘り下げてみましょう。
アルゴリズムによる最適化
TMSの配車最適化機能は、高度なアルゴリズムによって実現されています。これは、数理最適化やヒューリスティクスといった技術を用いて、膨大な組み合わせの中から、コストや時間、積載率などの制約条件を満たす最適な解を導き出すものです。AIや機械学習を活用することで、このアルゴリズムはさらに進化し、より複雑な状況に対応できるようになっています。
APIを活用したシステム連携
現代のTMSは、API(Application Programming Interface)を通じて、他のシステムとシームレスに連携することが不可欠です。APIとは、異なるソフトウェアやアプリケーションが互いに情報をやり取りするための規約のことです。TMSは、WMS(倉庫管理システム)や基幹システム(ERP)、会計システムなどとAPI連携することで、手作業によるデータの二重入力や入力ミスを防ぎ、業務全体の効率を向上させます。
GPS・IoTデバイスによるデータ収集
車両追跡や運行状況のリアルタイム管理には、GPS(全地球測位システム)や、車両に搭載されたIoTデバイスが欠かせません。これらのデバイスから収集された位置情報や運行データ(速度、急ブレーキ、エンジン状態など)は、クラウドサーバーを通じてTMSに送信され、管理画面にリアルタイムで反映されます。これにより、管理者は正確な状況把握と適切な指示出しが可能になります。
まとめ
この記事では、TMS(輸送管理システム)の基本的な概念から、その多様な機能、導入メリット、そして実際の成功事例まで、幅広く解説しました。
TMSは、単に業務を効率化するだけのツールではありません。コスト削減、サービス品質向上、労働環境改善、そしてデータに基づいた経営改善まで、物流企業の競争力を高めるための重要な戦略ツールです。
もし、あなたの会社で「配車計画が非効率だ」「燃料費が高騰している」「ドライバーの負担を減らしたい」といった課題を抱えているのであれば、TMSの導入を真剣に検討する時期かもしれません。この記事が、今後の貴社の物流改革の第一歩となれば幸いです。
TMSの導入は、物流業界の未来を拓く鍵となります。ぜひ、これを機に、貴社の課題解決に最適なTMSを見つけてみてください。